第2回 ドーキンス進化論Ⅰ 利己的な遺伝子理論が作り出す世界観
さて、今回からは、ドーキンスが作り上げた進化論的世界観についてまとめていきたいと思います。ドーキンスは生命個体を生存機械、遺伝子の乗り物と表現し、遺伝子こそ自然淘汰の世界における主人公であると考えたことは、前回紹介しました。また遺伝子に「利己的」というレトリックを用いることで、あたかも遺伝子どうしが生きて争い合っているかのような印象操作をしているようにも見えます。そもそも、進化を論ずる際になぜ遺伝子がそこまで重要なのでしょうか?
最初の生命は間欠泉で生まれた「自己複製子」から
ドーキンスは「利己的な遺伝子」概念を説明するため、生命のはじまりを以下のように論じます。最初の生命の始源は、火山の噴出口付近の間欠泉と呼ばれる水溜りのような場所で高密度のアミノ酸が集まってできた分子であった、と。
あるとき偶然に、とびきりきわだった分子が生じた。それを「自己複製子」と呼ぶことにしよう。それは必ずしも最も大きな分子でも、最も複雑な分子でもなかっただろうが、自らの複製を作れるという驚くべき特性を備えていた。
リチャード・ドーキンス. 利己的な遺伝子 40周年記念版 (Japanese Edition) (Kindle 版.No.801-803) (以下、著書名省略).
この自己複製子は、やがて間欠泉内で増えに増え、まとまっていきました。ときにコピーミスが起こって変種が現れ、ミスが起きていない複製子よりも生存に有利に働くこともありました。能動的な自己複製を繰り返していくうちに、自己複製子はより生存に適する機能を獲得していったというのです。例えばあるときは複製子を覆う核を獲得したり、代謝を獲得したり、細胞を作り上げてその細胞を組み合わせて生命を作り上げたり、と言った具合です。そのように自己複製子は歴史の中で、体を獲得し、自分は遺伝子として核内に閉じこもって、生命活動に間接的に関わるように、「進化」していったのです。
自己複製子の変種間には生存競争があった。それらの自己複製子は自ら闘っていることなど知らなかったし、それで悩むことはなかった。この闘いはどんな悪感情も伴わずに、というより何の感情も差し挟まずに行なわれた。だが、彼らは明らかに闘っていた。(中略)自己複製子は存在を始めただけでなく、自らの容れ物、つまり存在し続けるための場所をも造り始めたのだ。生き残った自己複製子は、自分が住む生存機械(survival machine)を築いた者たちだった。自己複製子の変種間には生存競争があった。
(同No.893-905)
通常、生存闘争と聞くと、個体同士、種同士が争っているように聞こえるでしょう。しかしもっと根源的には、その個体(乗り物)を作り上げる遺伝子同士が戦っているというのです。
例を挙げて説明します。働き蟻は自分の集団に対して献身的に働きますが、ドーキンスに言わせれば、無条件に利他的行動をしているわけではありません。自分が持っている遺伝子は、同じ巣穴の他の蟻と共有しているため、もし天敵が巣を襲撃して全滅したら、遺伝子を次の世代に残すことはできません。そこで、「蟻」をつくっている利己的な遺伝子たちは、個体別に役割を分担することにし、ある個体群には、利他的行為をさせることを選びました。働き蟻が巣穴の蟻を守って死んだとしても、その他の蟻がもつ(自分の)遺伝子が生き残り、結果として後代にバトンタッチされていくのです。
こうすることで利他的行為をしない蟻の群れの遺伝子に比べ、利他的行為をする遺伝子のほうが結果的により多くの遺伝子を次世代に繋ぐことができるのです。そうして、利他的行為を指示する遺伝子が生き残っていった、というわけです。
この点に関して、自然淘汰という力は、遺伝子に働いているのではなく、個体に働いているんだ、あるいは種をはじめとする集団に働いているんだという考えもあります。しかし、淘汰の単位を個体以上としてしまうと、利他的行為をする個体は生存闘争の世界ではいわゆる「お人好し」個体は真っ先に淘汰の対象となってしまい、うまく自然に適応できないという批判があります。そこで淘汰の単位を遺伝子とすることによって、「利他的行為=遺伝子の利己的行為」と説明できるようになったのです。こうして全ての生命の行動原理を合理的に説明しようとしたのです。生命は遺伝子レベルから「利己的」であり、いかなる行動も生物学的には生存と繁殖のための戦略的な行為に過ぎないのだと結論づけたわけです。
この進化論的視点を、ドーキンスは人間にも例外なく当てはめます。私たちには心と体がありますが、それらは全て遺伝子の所産であり、生存のための発明品だと彼は断言します。心の思惟に本質的な意味などなく、生命の神秘、自然の華美などは偶然の産物でしかないと切り捨てるのです。
宇宙には、デザインも、目的も、悪も善もなく、ただ無慈悲な無関心があるに過ぎない。
(Dawkins,R. River out of Eden: A Darwinian View of Life, London: Phoenix (1995), p.133)
精神は脳髄の所産と論じたのはマルクスですが、まさにこの観点を生物学的に論じ切ってしまったのがドーキンスだと言っていいでしょう。
人間の無条件的利他的行為をどう説明?
確かに、私たちは生きていれば自己本位に生き、自己実現を求め、時には他者とぶつかることもあるものです。しかし、人間にはもっと本質的で目的を指向する心があるのです。もし人間も自分の遺伝子の生存と繁殖のためという条件付きでしか行動しない存在であるとすれば、人間世界に多々見られる無条件的利他行為はどのように説明したらいいのでしょうか。自分の生存を諦めて他者を愛する行為に、私たちは胸打たれるものですが、それは、心の中にある「他者のためにいきたい心」が揺さぶられるからなのです。
ドーキンスは、遺伝子中心主義の進化論的論法によって、自然選択を万能の理論とみなします。そうして全ての生命を利己的な遺伝子の観点から説明し、目に見えない世界の一切を否定するのですが、都合のいい事実を拾い上げてつなぎ合わせた偏った思考であると見るべきでしょう。
次回は、ドーキンスの自然選択万能主義から出てくる生物行動理論の大枠について考えてみたいと思います。
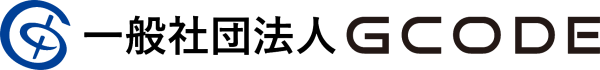






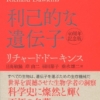





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません